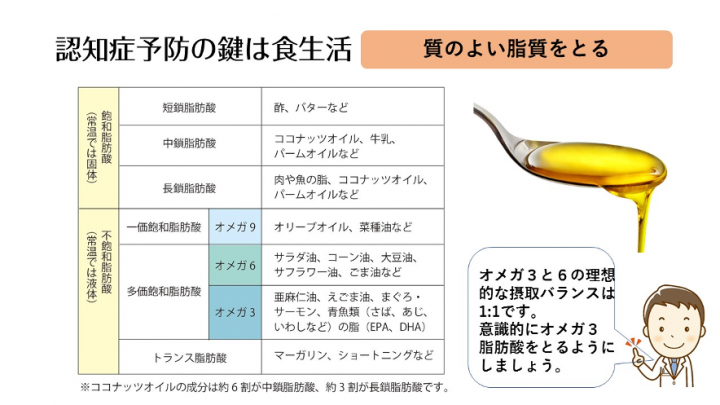2017.4.7 金曜日
小泉武夫さん講演会 2017年3月4日 江戸の健康食(前編) 発酵と日本人の知恵

2017年3月4日、社)日本アンチエイジングフード協会主催の講演会にて、発酵学、食品文化論、醸造学・縄文食研究の日本の第一人者である東京農業大学名誉教授・小説家である小泉武夫さんをお招きして、様々なお話を伺いました。日本人の食と暮らしの知恵が豊かに息づいていた江戸時代のお話を中心に、多様な食文化を探して世界を巡ってきた小泉さんならではの「健康に生きるための食」のヒントが盛り沢山。ユニークな論説とわかりやすい語り口に、来場者全員が聞き入っていました。
薬としても人々の健康を支えてきた「発酵食品」
菌の働きが人間の体に良い影響を与える不思議
「生まれたときからアンチエイジングフードに囲まれていた」という小泉武夫さん。福島県会津の造り酒屋に生まれ、お酒はもちろん味噌などを自家でつくり、様々な工夫のもと、日々の食生活に取り入れていたといいます。
「味噌樽に昆布を差し込んで漬け込んでおくと、昆布には味噌の、味噌には昆布の旨みが染み込んで大変おいしくなるんです。引き上げた昆布を細く切れば、それだけで味わい深いごはんのおかずになりました」
そうした原体験が「食の冒険家」としての活躍の土台になっているのでしょう。小泉さんが最も愛してやまない食品が、納豆やヨーグルトなどの「発酵食品」です。ゆでた大豆も牛乳も放置しただけでは腐敗してしまうのに、納豆菌や乳酸菌が入るとなぜか腐敗せず、えもいわれぬ旨みを生み、人間が作り出せないようなビタミンやミネラル、アミノ酸、酵素などの栄養素を作り出すーー。その「発酵」の不思議さを小泉さんは次のように語ります。

「私たちの体の細胞と発酵の菌は、ほぼ同じくらいの大きさです。それぞれが似た活動を行っており、ある菌の活動を私たちの体内に取り込むと“いい効果”がある。それが『発酵』なんです。一方、人間の体に悪影響を及ぼすのが『腐敗』です。同じ菌の働きなのに全く逆の働きになるのは、不思議としか言いようがありません」
それでは発酵菌と腐敗菌(悪玉菌)とでは、どちらが強いのでしょうか。悪玉菌の代表格として病原性大腸菌 O157、中でも感染力が高い菌ををある企業からから取り寄せ、小泉さんの保有していた17種類ほどの納豆菌と“闘わせた”ところ、圧倒的に納豆菌が勝利したといいます。
また、小泉さんがカンボジアの奥地を訪問した際、村の歓迎料理を食べた若いメンバーは全員酷い下痢になったにも関わらず、小泉さんはまったく平気だったといいます。それも初めてではなく、どんな僻地に行って何を食べても当たらない。小泉さんは、その理由を「納豆菌のおかげではないか」と推測します。

「発酵菌が入った食べ物はそうそう“腐る”ことはありません。私の場合、8ヶ月間冷蔵庫にあった納豆を発見したときは、すりばちで擦って煮干し粉と合わせて“ふりかけ”としていただきます。牛乳もヨーグルトやチーズにして環境を整えれば、まずは腐敗菌を寄せ付けないのです。事実、グルジアにクルド族をたずねた際に貰い受けた170年前のチーズは、かなり乾燥していたものの、風味も味わいも良質なチーズそのものでした」
同様の発酵食品に日本でも出会ったといいます。それは和歌山県の新宮市横町にある東宝茶屋に伝わる「さんまの熟れ鮓」。薬壷に入っており、江戸時代には新宮参りの帰りに「薬」として購入して帰ったというものでした。また、滋賀県立大学で「環琵琶湖文化論」を開講した際に「鮒鮨」の調査を行ったところ、産後の肥立ちや下痢・便秘などの改善など幅広く使われていたことがわかりました。滋賀県湖北の余呉湖のほとりにある料理宿「徳山鮓」に宿泊した際にも、鮒鮨で一気に風邪が治るという経験をしたといいます。
「39度以上の熱が出ているにも関わらず、熱めの風呂に入れというので、入って出てきたら、部屋では火鉢に鉄瓶がかかり、蒸気でもうもう。その鉄瓶からほぐした鮒鮨に熱湯を注いで、丼いっぱい食べたところ、夜中に汗だくになって3度も目が覚めました。でも、朝にはケロリと治っていたんです。そうした経験もあって、新宮市の『さんまの熟れ鮓』および『徳山鮓』を取り寄せて冷凍庫に備え、風邪の常備薬にしています」
さらに、伊豆諸島で作られている「くさや」も紹介されました。「くさや」とは、ムロアジを発酵液につけたもので、あまりに強烈な匂いのためにその名がついたというもの。現地では風邪や下痢などの体調不良の際には、この発酵液である「くさや汁」を飲み、切り傷などの外傷にまでつかわれています。発酵液にたっぷりと含まれた「天然の抗生物質」に秘密があるというわけです。
では、現代にも活かしたい江戸時代の健康食はどんなものなのでしょうか、
詳しい内容は後編に続き来ます。